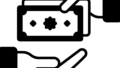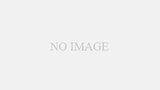豊橋の税理士 提中です。
相続対策というと、いかに相続税を減らすかに目が行きがちです。
しかし、本当に重要なのは相続税の減額ではないと常々私は考えています。
相続の発生によりこれまで仲の良かった親族の人間関係に亀裂がが入らないようにすること。
最も優先すべきこととしては、この1点に尽きると思っています。
人間ですから誰しも貰えるものは多く貰いたいという気持ちになるのは当然です。
被相続人の意思表示がなければなおさらのこと。
少なくとも法定相続割合に見合う財産は取得したい。それが多くの方の心情であると推察します。
しかし、生前に被相続人の意思表示があればまた違った結果になります。
その点から遺言書は生前に作成することが重要であるとこのブログでも遺言書をテーマに
記事を書いてきました。
遺言書を作成しない場合に起きる悲劇とは。後でもめないために遺言書はしっかり作りましょう。
自分で遺言書を作成しよう。自筆証書遺言、公正証書遺言作成のポイント
遺言書により残された方々に争いが発生することを予防した後は、相続が発生したときに
相続税を問題なく納めることができるのかを事前に計算しておくことが重要です。
特に長く事業に注力してきた方については、相続財産の大半が自社株式であることも散見されます。
非上場株式は上場株式に比べ圧倒的に換金性が低い株式です。また、仮に第三者に譲渡できるとした
場合でも、株式の譲渡により議決権比率が低下し事業承継に悪影響を及ぼすことがあります。
そんなときの一つの対応策としては、発行法人への自己株式の売却が有効となります。
今回は、自己株式取得する際の課税関係と、自己株式取得するために必要となる手続きを
法務面と税務面の両面から見ていきたいと思います。
自己株式を発行法人に売却した場合の課税関係

自己株式を譲渡した場合、売却代金から資本金等の額を差し引いた金額は利益の払い戻し扱いとなり、
配当所得とみなされます(みなし配当)
非上場会社からの配当所得は総合所得として他の所得と合算され、最大55%もの高税率で所得税等が
課されます。
自己株式という株式の譲渡であるため、譲渡所得に該当しそうなものですが、譲渡所得は資本金等から
取得費を差し引いた金額となることに注意が必要です。
そのことを知らずに自己株式を譲渡すると多額の税金が課され、思った以上に手元に残る資金が
少なる可能性があるためご注意下さい。
相続発生後一定期間内に自己株式を発行法人に売却した場合の特例

自己株式を譲渡した場合の課税関係については上述した通りです。
しかし、相続発生後3年10ヶ月以内に自己株式を発行法人に売却した場合には
所得税の税負担を低減させる特例措置を受けることが可能となります。
特例措置は2つあります。
①みなし配当課税されない特例
②相続税額を取得費に加算できる特例の二つです。
これらは、相続発生時に相続税納税資金がなく、自己株式を譲渡せざるを得ない場合の救済措置的
位置づけです。特に②の特例措置が株式の納税資金化に非常に力を発揮します。
上図を見ていただくとわかる通り、相続のタイミングで自己株式を譲渡すると、みなし配当課税が
されなくなります。売却代金から取得費を差し引いた金額が譲渡所得とされ、20%の固定税率で
所得税等が計算されます。
自己株式取得のために必要となる手続きについて
法務面の手続き
後日記事にまとめます。
税務面の手続き
株式を発行法人に売却するにあたり、相続人が所有する株式の株価算定が必要となります。
自己株の売買も、個人から法人への株式譲渡の一つであるため、財産評価基本通達ではなく、
所得税基本通達に基づく株価算定が必要となる点に注意が必要です。
相続発生後に自己株の売買を行う場合、相続税申告のための株価算定が実施済みかと思います。
しかしながら、それは財産評価基本通達ベースで算定された株価であるため使用することはできません。
【関連サービス】
弊所では自己株式の売却に必要となる株価算定、そして自己株式の法務手続きまでワンストップで
対応致します。詳細は下記のリンク先にてご確認下さい。